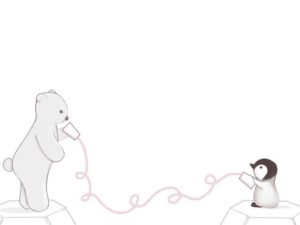共著者 山口一郎の、出版への想い(I)
――このインタビューでは、この本で伝えたかったメッセージについて伺っていきたいのですが、この『職場の現象学』を書くことになったきっかけはなんだったのでしょうか?
山口:そもそも職場の現象学を書くことになったのは、7~8年前に共著者である露木さんに職場の現場に連れて行ってもらったことが大きなきっかけでした。
――様々な職場の現場をご覧になってきたとお聞きしていますが、現場で起こっていることは現象学の視点から見るとどう見えるのでしょうか?
現象学から見てどう見えるのかというのは、簡単に言うと「僕がどう見ているのか」という事なのです。たまたま、僕が現象学をずっとやってきたので、そうすると自分の生活の癖のようになっている。つまり、自分が生きるうえでいろいろな経験や体験をしてきていますけれども、生き方を反省してきたときに、「どうしてこんなふうにしたのだろうか」と。
長い話になって恐縮ですけれども、そもそも哲学ってやはり人が生きていくことの自覚だと思うのです。「どんなふうにして生きているのかな」ということなのですが、その時に社会的な価値観も出来上がってくるから、電車で人に揉まれて高校へ通っていた頃から「何で人ってこんなふうにして働かなければならないのだろう」と心に思っていたのです。
そうして、哲学の本を読みだした頃から、そもそも働くことは「食う事のために働くのか、働くために食うのか」という理屈をこねだす頃に、「人が生きることや人が働くことは全体の人生から見てどういう意味があるのか」ということは、いつも離れないテーマなのです。
僕の知っている職場というのは大学という狭い領域ですので、実際、どうやって皆さんがいろいろな職場の中で苦悩しながら喜びを交えて過ごしていらっしゃるのか、実際に経験する余裕は無かったのです。
だけれども、それを露木さんが僕の所で博士論文を書くという事をきっかけにして、正確に言えば野中先生の元で書いていらっしゃるときに、「メルロ=ポンティやフッサールの現象学的な見方が役立つよ」と。これは野中先生の慧眼です。人が働くことにおいて反省をする際に、こういう哲学者がいて身体性や人間関係の事について深く突っ込んだ反省をしているという事実を、たまたま僕の博士論文をお読みになって、まだ僕が49歳の若造の頃、わざわざ尋ねてくださったのです。
そこから、職場の現象学への入り口が出来上がったのです。野中先生の下で博士論文を書いていらした露木さんが、一体全体、フッサールとかメルロ=ポンティってどういう事を考えているのだろうという事で僕のゼミに来てくれたのです。それがきっかけになりました。「現象学ことはじめ」を最初に読んでくださったのは露木さんでしたから、その時のつながりもありますし、そうやっている僕を、言ってみれば職場の現場に連れて行ってくださったのが露木さんな訳です。
――現場に行った経験で印象に残っているものは何ですか?
山口:そのなかで一番身近に感じたのは桜えび漁です。あの時もスムーズにいったわけでは無くて紆余曲折があって、職場の中での苦しみというものが、直に伝わってきたのです。
これは実際にどうなっているのか見てみないといけないという事で、船に乗ったのです。船と言っても小さな小舟で、大波小波を乗り越えて漁場まで行く。そして、実際にどのように漁をしているのか、最後に競りで売られて、その商品が買い手までいくのか。綺麗な富士山が見えている由比の浜に獲ったばかりの桜えびを干している。漁の現場の悩みと、買った人がそれをどうやって商品にして、売れるようにするのかという一貫したプロセスを体験させてもらったのです。
仲買問屋さんと漁師さんとの関係とか、漁師と船主と問屋との団交の場面とかね。本当に生の現実に動いているさなかで、どれだけ量が獲れるのか獲れないのかということしか頭にない漁師たちの間で、どんなことが起こっているのかということを直に経験できたわけです。
他にもいろいろな所に行きました。とりわけ印象に残っているこころみ学園に行ったとき、実際に露木さんは経験したこともあるのだけれども、園長さんからの話でいろいろなケースを聞いて、本当に働くという事のぎりぎりのところ、人が支え合っている現場。「仕事」と言う言葉は、要するに「生きてお互いに支え合っていく」という現実ですよね。あるいは、そう言う言葉で言って良いのかどうかわかりませんが、「仕事を通して共に生きていく」というギリギリのエッセンスみたいなこと。どうやって人はお互いに支え合って生きていけるのかという現実に触れる機会を与えてくださったのも露木さんなのです。
ですから、この現実に哲学たるものがどのような分析をかけて、個々の具体的な問題に対する回答を与えることができる、そのような哲学であり得るかどうか、つまり、人間の哲学的反省の本質が問われるわけです。
――そのうえで、哲学は現実に対してどういう立ち位置なのでしょうか?
山口:哲学は、仕事をしている人々にとって、あるいは人間関係に悩む人々にとって、簡単に言うと「何の役に立つのか」ということですね。問題と言うのは、解決されなければ問題解決にならないのですから。いろいろと理論を述べたとして、「こうなっているのですよ」と。人間の動きをロボットみたいに解析して、「こうやって電気を通せば、動くんですよ。人間の動きに近いでしょう」というように、動きの仕組みを自然科学で作り上げてまねごとのロボットを作ったところで、人が仕事で悩んで苦しんで仕事をして生活しているということの根本的な意味、つまり「人のために役立つ」とか、そもそも働き口が人と一緒になって仕事が出来るという、「生きている事の根本的な動機はどこにあるのか」には迫れません。
今は、新型コロナウィルスの問題が世界中の問題になっているけれども、人間の生死というギリギリの所に当たって、「哲学は一体何のために役に立つのか」と問われるのです。これが本当の哲学の問いな訳ですから。それにどう応じることが出来るのか書いてみたのが、まずは「現象学ことはじめ」を書いた動機です。そして野中先生との『直観の経営』、そして『職場の現象学』でも、現象学はどういうものかということを説明するための、根本的な動機になっているのは、一体人が生きて働いていくという事の根本的な意味を問うことなのです。『職場の現象学』の副題にもなっていますが、「仕事をすることの意味を問い直す」という動機で書き始めたのです。
――少し今までの話をまとめてお聞きしたいと思いますが、いろいろな現場を見てきて、こころみ学園のお話や桜えび漁のお話がありましたが、そういった人が生きていくことや働いていくこと、仕事を通して生きていくことに対してその悩みに哲学はどのように答えていくのか、問題解決にどう寄与するのかという話があったと思います。「働くことの根本的な動機に対して職場の現象学を上梓しよう」という事になったということ、ポイントはそこに行き着くのだと僕は理解したのですが、まずそれは合っていますか?
山口:上手におまとめになっていると思います。
――山口先生から見て、今一度この場で先生が今回本をお書き終わりになって、もう一度振り返って、こころみ学園の皆さんであったり、桜えび漁の皆さんであったり、そういう人たちにも思いをはせつつ、人の働くことの根本的な動機、そこに哲学は何を答えたのかということを、先生の言葉でもう一回語って頂くと、どういう解がそこには出て来ますか?
山口:第一章で「本当の一人になれ」という所があるじゃないですか。要するに「本当に悩め」と。「お前、本気か?本気ぶってんじゃないよ」と。人はいくらだって「やらなきゃいけないから」と格好つけて自分の仕事のアリバイみたいにする。そのような悩みは本当の悩みじゃない。本当に苦しくてどうしようもなくて、解決したいという本気の気持ちがあるならば、初めて開けてくるものがある。
だから、現象学がまず皆さんに要求するのは、「本当の一人になれ」という、絶対的な懐疑の例を出しました。デカルトを第一章に持って来ました。それはどういう事かというと、要するに「哲学は真善美を扱う」と言うのだけれども、一番の根幹になっているのは、「真理」ということなのです。普遍的な誰にでも通じる真理ということです。
それを求めてデカルトは、ノイローゼになりかけた。そのノイローゼになりかけたというなりかけが半端じゃない。様々な諸学問の最先端を全部学んだ上で、自然科学でさえ、神学でさえ疑った。全てが何が何だか分からなくなっちゃった。
どういう事かというと、普通は自然科学の、例えば百円玉を自販機に入れれば飲み物が出てくるように、自然科学に対する確信は揺らがない。お医者さんにかかった時に、学問を研究しているお医者さんを信用するわけです。西洋の学問の自然科学の上に立った医療で治療をしてもらう。つまり、自然科学に対する一般的な確信みたいなものは、現代社会において揺らぎないものとしてある。
その自然科学の基礎になっている数学でさえ全知全能の神様がいて、人間を騙しているかもしれないとデカルトは考えた。どうしようもない、神も仏もあるものかというところです。言ってみれば、人が悩むときの究極の悩みというか。ただ、幸福な事に、情緒的な意味での悩みではなかった。哲学的な悩みです。本当の真理と言うのは何なのかということを、ありとあらゆる可能性をめぐって、神がいるかもしれないけれども、神が私をだましたところで、絶対に間違いない唯一のものがある。それが「我思うゆえに我あり」です。これがギリギリの個人になれという意味です。方法的に一人になると言ったときに、「本気になって一人になるつもりがあるのなら、神も仏もあるものかというギリギリのところまで全部悩み尽くせ」と言うのです。
だって、神様がいるかどうか分からないじゃないですか。わからないことも疑問の可能性として含んだ、徹底的な懐疑です。かもしれないことをすべて含みいれた疑問です。それを通して、絶対に確実と言われるものこそ、本当に人が孤独になったときに藁をもつかむ思いで掴むことのできる、自分にとって絶対的に間違いのない真理じゃないですか。これが「我思うゆえに我あり」の意味です。今この瞬間に「考えていること」と「考えている私がいる」ということ、つまり一瞬一瞬に考えた内容とそうやって考えている自分がいるということ。これは絶対に揺るぎないということなのです。ですから、どんな懐疑論者が出てきて、「そんなの分かるかよ」と言ったところで、「そんなの分かるかよ」と言った瞬間の自分の「『分かるかよ』と言ったそれは何?」、「それは確実なことでしょ?」ということです。
これはまだフッサール現象学の入り口に過ぎません。続編もご期待ください。